|
|  |
| 「文正草子」屏風(「ぶんしょうそうし」びょうぶ) 江戸時代作 |
| |
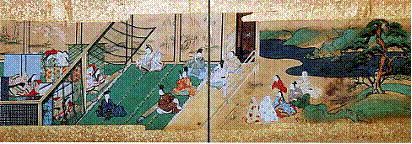 |
|
・解説
「文正草子」は,本県の鹿島(今の鹿嶋市)に所縁の深い御伽草子です。かつて鹿島大明神の大宮司に仕えた文正は、塩焼きとして成功し並びなき長者となります。子宝に恵まれない彼は、鹿島大明神に祈願し、二人の女児を授かります。やがて類無き美女に成長した二人の噂は京にまで及び、関白の子(二位の中将)の心を焦がします。
写真の場面は,御簾の向こうの娘を見たいと願いつつ、二位の中将らが管弦を奏でているところです。折しも,一陣の風によって御簾が翻り、噂に違わぬ娘の美しさに、中将はすっかり心を奪われてしまいます。二人はめでたく結ばれ、後には妹も帝に召される、というめでたさに終始する物語です。
その内容から、正月の草子読み初めの吉書として用いられたり、婚礼調度にも加えられました。 |
| |
| 戻る |
|